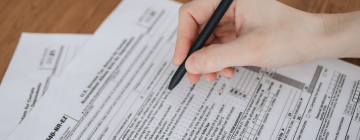信託契約の具体例:不動産を信託する際のポイント
家族信託は、将来の財産管理や承継を円滑に進めるための有効な手段です。
特に不動産を信託することで、認知症による財産凍結の回避や相続時の手続きをスムーズにすることが可能になります。
本記事では、不動産を信託する際の具体例と、信託契約のポイントについて解説します。

1. 不動産を信託する目的とメリット
不動産を信託する主な目的は、財産管理の継続性を確保し、相続時のトラブルを防ぐことです。
1-1. 認知症による財産凍結の防止
高齢者が認知症を発症すると、本人の判断能力が低下し、不動産の売却や管理ができなくなることがあります。
家族信託を活用すれば、受託者(家族)が不動産の管理や処分を継続できるため、財産凍結のリスクを防ぐことができます。
1-2. 相続手続きの簡略化
通常、不動産の相続には遺産分割協議や相続登記が必要ですが、家族信託を活用すれば、信託契約で決めた通りに財産を承継でき、相続手続きをスムーズに進められます。
1-3. 不動産の一元管理が可能
複数の相続人がいる場合、共有名義にすると売却や管理が複雑になります。
信託を活用すれば、受託者が管理・運用を一元的に行えるため、不動産の有効活用が容易になります。
2. 不動産を信託する具体的なケース
2-1. 親が所有する自宅を信託するケース
【事例1】
– 委託者(信託を設定する人):父(75歳)
– 受託者(財産を管理する人):長男
– 受益者(財産の利益を受ける人):父
– 信託の目的:父が認知症を発症した場合でも、長男が自宅を管理し、将来的に売却も可能にする。
– 終了時の処理:父の死亡後、信託を終了し、長男が相続する。
<ポイント>
– 信託契約に「父が住み続ける権利」を明記することで、本人の生活を守る。
– 信託終了後の所有権の帰属先を明確にしておく。
2-2. 収益不動産を信託するケース
【事例2】
– 委託者:母(80歳)
– 受託者:長女
– 受益者:母
– 信託の目的:母が所有する賃貸アパートの家賃収入を長女が管理し、母の生活費に充てる。
– 終了時の処理:母の死亡後、信託を終了し、アパートを長女と次男で相続する。
<ポイント>
– 信託財産からの収益(家賃収入)を受益者(母)に渡す仕組みを明確にする。
– 母の死亡後、相続人が円滑に不動産を承継できるよう、受益者の変更や信託終了時の処理を契約に記載する。

2-3. 事業用不動産を信託するケース
【事例3】
– 委託者:会社経営者(70歳)
– 受託者:次世代経営者(息子)
– 受益者:経営者本人
– 信託の目的:事業用の土地・建物の管理を息子に引き継ぎ、経営の安定化を図る。
– 終了時の処理:経営者の死亡後、息子が事業用不動産を継承する。
<ポイント>
– 事業の継続性を確保するため、経営者の判断能力が低下しても運用が続けられる契約内容にする。
– 経営者の死亡後、会社の資産として円滑に移転できるよう、信託の終了条件を明確にする。
3. 不動産信託契約のポイント
3-1. 受託者の選定
受託者には信頼できる家族を選ぶことが重要です。
不動産管理の知識がある人が適任ですが、管理が難しい場合は専門家(信託会社や行政書士)を活用するのも選択肢です。
3-2. 信託の終了条件を明確にする
信託の終了条件を明記しておかないと、信託が不要になったときに処理が難しくなる可能性があります。
例えば、
– 受益者(親)の死亡時
– 一定の年数が経過した場合
– 信託の目的が達成されたとき
3-3. 税務上の考慮
不動産を信託する際には、登録免許税や不動産取得税などの税負担が発生する可能性があります。
また、信託財産から発生する収益の課税関係も考慮する必要があります。
3-4. 遺留分対策
家族信託は、遺言と異なり「遺留分」の対象となる可能性があります。
相続人間のトラブルを避けるため、信託契約の内容を十分に検討し、遺留分を考慮した遺言書の作成も併用することが望ましいです。

4. まとめ
不動産の信託は、認知症対策や相続の円滑化に非常に有効な手段です。
しかし、契約内容の設定を慎重に行わないと、意図しないトラブルを招くことがあります。
受託者の選定や終了条件の明確化、税務面の対応などをしっかりと検討し、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。
不動産の信託を検討している方は、まずは財産の状況を整理し、適切な信託契約を設計することから始めましょう。
参照記事等
司法書士法人TOUKIのウェブサイト「家族信託の具体例と解説家族信託の具体例と解説」
(最終閲覧2025年4月16日)
家族信託研究所のウェブサイト「家族信託・民事信託の活用事例」
(最終閲覧2025年4月16日)