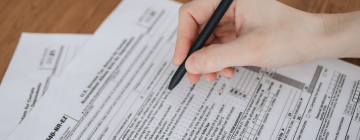家族信託の基礎:認知症対策としての家族信託とは?
認知症になると、自分の財産を管理することが難しくなり、不動産の売却や銀行手続きなどができなくなることがあります。
家族信託は、このような問題を未然に防ぎ、家族が安心して財産を管理できる仕組みの一つです。
本記事では、家族信託の基礎知識と認知症対策としての活用方法について解説します。

1. 家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、管理・運用・処分を任せる制度です。
信託契約を結ぶことで、財産の所有権は信託契約に基づいて移転し、財産の管理者(受託者)が定められた目的に従って運用を行います。
(1) 家族信託の基本構造
- 委託者:財産を信託する人(例:親)
- 受託者:財産を管理・運用する人(例:子ども)
- 受益者:信託財産の利益を受ける人(例:親または家族)
2. なぜ認知症対策として有効なのか?
(1) 財産管理の継続が可能
認知症になると、自分の意思で契約を結んだり、不動産を売却したりすることができなくなります。
しかし、家族信託を事前に設定しておけば、受託者(例:子ども)が代わりに管理を続けることができます。
(2) 成年後見制度よりも柔軟な運用が可能
成年後見制度では、後見人が家庭裁判所の監督を受けながら財産管理を行いますが、利用の自由度が低く、手続きが煩雑です。
一方で、家族信託は契約に基づいて柔軟に財産を管理できるため、より実践的な認知症対策になります。
(3) 不動産の円滑な管理が可能
認知症を発症すると、不動産の売却や賃貸が難しくなります。
しかし、家族信託を活用することで、受託者がスムーズに不動産の運用や売却を行うことができます。

3. 家族信託の具体的な活用方法
(1) 高齢の親が持つ不動産の管理
高齢の親が自宅や賃貸物件を所有している場合、家族信託を活用することで、子どもが受託者として不動産の管理や売却を行うことが可能になります。
(2) 生活費や医療費の支払い
家族信託を利用すると、信託財産を活用して受益者(親)の生活費や医療費を確保することができます。
これにより、親が認知症を発症しても、財産を有効に活用できます。
(3) 事業承継への活用
中小企業の経営者が高齢になる場合、家族信託を活用して、後継者にスムーズに事業用財産を承継させることができます。
4. 家族信託の注意点
(1) 適切な契約内容の設定
家族信託は自由度が高い制度ですが、契約内容を慎重に設定しないと、意図しない財産の使い方がされる可能性があります。
専門家に相談しながら契約内容を決めることが重要です。
(2) 税務面の影響
信託財産の移転に伴い、贈与税や相続税が発生する可能性があります。
税務面の対策をしっかりと考慮することが必要です。
(3) 信託の終了条件を明確にする
信託の終了時に財産を誰に帰属させるかを契約に明記しておくことで、相続のトラブルを防ぐことができます。

5. まとめ
家族信託は、認知症対策として非常に有効な手段です。財産管理の継続性を確保し、成年後見制度よりも柔軟に運用できる点が大きなメリットです。
しかし、契約内容の慎重な設定や税務面の対策が必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
早めの対策を行い、将来の財産管理に備えましょう。
参照記事
相続・家族信託ガイドのウェブサイト「家族信託は認知症でも可能?判定基準と認知症発症前後の対応方法を解説」
(最終閲覧2025年3月23日)
家族信託のおやとこのウェブサイト「家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説」
(最終閲覧2025年3月23日)