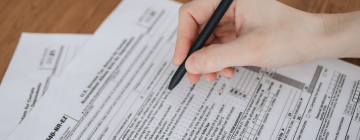相続の基本知識:遺言書の必要性と作成のポイント
相続の手続きにおいて、遺言書は非常に重要な役割を果たします。
遺言書があることで、相続人同士の争いを防ぎ、円滑な財産の承継が可能となります。
本記事では、遺言書の必要性や作成のポイントについて解説します。

1. 遺言書の必要性
(1) 相続トラブルを防ぐ
遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って分割されます。
しかし、これが相続人全員の意向に沿うとは限らず、遺産分割協議が長引く原因となることがあります。
遺言書があれば、故人の意思が明確になり、不要な争いを防ぐことができます。
(2) 法定相続と異なる分割を可能にする
遺言書がない場合、民法に定められた法定相続分に基づいて財産が分配されます。
しかし、たとえば特定の相続人に多くの財産を渡したい場合や、相続人以外の人(内縁の妻や孫など)に財産を譲りたい場合には、遺言書による指定が必要となります。
(3) 事業承継をスムーズに行う
中小企業の経営者の場合、会社の株式や事業用資産の承継を円滑にするために、遺言書を作成しておくことが推奨されます。
これにより、後継者を明確にし、会社の経営が混乱するのを防ぐことができます。
2. 遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の3つの種類があります。
(1) 自筆証書遺言
- 遺言者が全文を自筆で記載する
- 2020年の民法改正により、財産目録はパソコンで作成可能
- 費用がかからず手軽に作成できるが、方式不備による無効のリスクがある
- 2020年から法務局での保管制度が開始され、紛失や改ざんのリスクを軽減可能
(2) 公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成し、証人2名の立会いが必要
- 内容の不備がなく、裁判所での検認手続きも不要
- 費用はかかるが、最も確実な方法
(3) 秘密証書遺言
- 内容を秘密にできるが、公証人が関与するため形式の確認は可能
- 方式の不備により無効となる可能性がある

3. 遺言書作成のポイント
(1) 遺言の内容を明確にする
財産の分配について、誰に何を相続させるかを具体的に記載しましょう。
また、遺言執行者を指定すると、手続きがスムーズになります。
(2) 法的要件を満たす
遺言書には、日付、署名、押印が必要です。
自筆証書遺言の場合、全文を自筆で記載しなければなりません。
公正証書遺言を選ぶ場合は、公証人と証人2名が立ち会う必要があります。
(3) 定期的に見直す
家族構成の変化や法改正に対応するため、遺言書は定期的に見直し、必要に応じて更新しましょう。
4. まとめ
遺言書は、相続争いを防ぎ、財産の承継をスムーズにするために重要な役割を果たします。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴を理解し、自分に合った方法で作成することが大切です。
また、定期的に内容を見直し、家族の状況に応じて適切な形で遺言を残しましょう。
参照記事
相続税のチェスターのウェブサイト「遺言書が必要な人リスト~なぜ必要?残すべき理由とは?~」
(最終閲覧2025年3月23日)
三菱UFJ銀行のウェブサイト「遺言書とは?作成が必要な状況や作成例、作成すべき理由などについて」
(最終閲覧2025年3月23日)