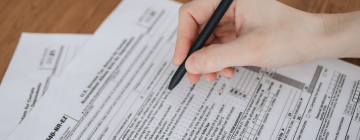成年後見制度とは?:家族信託との違いと選び方
高齢化が進む中で、認知症や障害により判断能力が低下した場合の財産管理が重要な課題となっています。
その解決策の一つとして「成年後見制度」があります。
しかし、近年は「家族信託」との比較も増え、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。
本記事では、成年後見制度の概要と家族信託との違い、選び方について解説します。

1. 成年後見制度の種類
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人の財産や生活を法的に保護する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります。
(1) 法定後見制度
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、以下の3種類があります。
– 後見(判断能力がほぼない)
– 保佐(判断能力が著しく不十分)
– 補助(判断能力が不十分)
後見人は家庭裁判所の監督を受けながら、本人の財産管理や契約手続きを行います。
(2) 任意後見制度
本人が元気なうちに「将来、自分の判断能力が低下したときに財産管理を託す人(任意後見人)」を契約で決めておく制度です。実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が認めたときです。
2. 家族信託との違い
成年後見制度と家族信託は、どちらも判断能力が低下した際の財産管理手段ですが、目的や運用方法に大きな違いがあります。
| 比較項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
| 主な目的 | 本人の保護と財産管理 | 財産の管理・承継の円滑化 |
| 開始時期 | 判断能力が低下した後(法定後見) | 判断能力があるうちに設定可能 |
| 管理対象 | 本人の全財産 | 信託契約で指定した財産のみ |
| 柔軟性 | 家庭裁判所の監督下で厳格 | 契約内容に応じて自由度が高い |
| 終了条件 | 本人の死亡時 | 契約で定めた条件により終了 |
| 費用 | 裁判所手続き・報酬あり | 契約時の費用のみ |
3. どちらを選ぶべきか?
成年後見制度と家族信託のどちらを選ぶかは、本人や家族の状況によります。以下のケースごとに適した方法を見ていきましょう。
(1) 成年後見制度が適しているケース
– 本人がすでに認知症を発症しており、判断能力が低下している
– 全財産の管理が必要であり、信託契約では対応できない財産がある(例えば年金の受け取りや医療契約など)
– 家庭裁判所の監督のもとで厳格に管理したい
– 悪徳商法や詐欺被害のリスクがある
(2) 家族信託が適しているケース
– 本人が元気なうちに将来の財産管理を決めておきたい
– 特定の財産(不動産や金融資産)だけを管理したい
– 後継者へのスムーズな資産承継を考えている(例えば事業用資産や不動産)
– 家庭裁判所の監督なしに、自由度の高い財産管理をしたい
(3) 併用するケース
成年後見制度と家族信託は、組み合わせて活用することも可能です。
– 生活費や医療費の管理は成年後見人に任せ、不動産などの資産運用は家族信託で行う
– 認知症発症後の財産管理は成年後見制度、発症前の財産管理は家族信託を活用する

4. まとめ
成年後見制度と家族信託は、それぞれメリットとデメリットがあります。
すでに判断能力が低下している場合は成年後見制度が適しており、将来に備えて財産管理を計画するなら家族信託が有効です。
また、両方を併用することで、より適切な財産管理が可能になります。
どちらを選ぶべきか迷った場合は、専門家に相談しながら、自身や家族の状況に合った方法を選びましょう。
参照記事等
成年後見はやわかりのウェブサイト「成年後見制度とは」
(最終閲覧2025年4月6日)
成年後見制度・成年後見登記制度のウェブサイト「Q1~Q2 「成年後見制度について」」
(最終閲覧2025年4月6日)